![]()
![]() ≪続≫
≪続≫
かっては、下誓多林を経て柳生にでる道を、柳生街道と云ったらしい。が、私は、通常
大慈仙、忍辱山、大柳生を経て、旧柳生城下へ至る道をとる。大慈仙から約3キロで
忍辱山の集落に達する。
誓多林といい、大慈仙といい、忍辱山といい、奇妙な地名が続いている。何れも佛法の
世界を現実に当てはめたからだろう。

そのひとつに忍辱山(にんにくせん)・円成寺があるが、街道のうち
でも最大のハイライトのひとつであると、私は、おもう。その宗教性に
おいても、その芸術性においても、ともに申し分はない。
その円成寺は全てが完全なまでに統一された、稀有に美しい古寺
ではある。
正面から平安朝の遺構である庭園をぬけ、急な石段を登ると、三間
一戸の桧皮ぶきの見事な楼門(重文、室町)にいきあたる。それを
くぐると、変化があって、かつ均整もとれた屋根をもつ本堂・阿弥陀堂
が現れる。
そして、そこには、ご本尊・阿弥陀如来坐像(国宝、藤原)をはじめ
として幾多の佛教芸術が生きた姿で安置されている。
殊に、運慶銘の大日如来坐像(重文、藤原)は、一品である。彼の若かりし
ころの作品ではないかとおもわれる。
とにかく、円成寺は、その格調も極めて高いお寺ではある。
なお、柳生街道を歩いていると、前にも触れたがしきりに野佛と出会う。
どいつも、こいつもさりげなく、つつましい顔のものが多く、親愛の情を
覚える。ここらでは、野佛も、まだ決して道から浮きあがってはいないのであろう。
この円成寺周辺にも極めて多い。
柳生街道もここまで来ると、全行程の、半分を消化したこととなる。
柳 生 の 里
円成寺のある忍辱山からの街道は、端正で重量感のあるお堂をもつ南明寺、
街道をへだてた、その斜め向かいには春日(大社)造りの本堂[重文]をもつ
長尾神社などを通っていく。柳生の殿様・但馬守が、そこで、洗濯をしていた
村娘・おふじの才気と器量をみそめて、妻に迎えたという伝説がある
おふじの井戸を経て、いよいよ柳生の里に至る。
かって、NHKの大河ドラマ“春の坂道”の舞台ともなった前後を
除いては、柳生の里は至ってのどかである(当時は“欲の坂道”と
まで悪口も云われた。) 道は美しくカーブし、水車が透明な水を
汲んでいる。
それにしても、どうしてこんな静かな山里が剣の聖地ともなり、柳生家が
その所領は1万石程度ながら天下に権勢をふるって、その兵法が正道についた
のか、私には、全く不思議な気がしないでもない。
その柳生の里には、映画やテレビでおなじみの独眼流(柳生)十兵衛が植えた
といういい伝えのある十兵衛杉(最近なくなった?) また、柳生史跡の中心
でもあり、極めて感慨をそそられる芳徳寺(柳生家の菩提寺)や立派な石垣を
もつ屋敷などが残っている。
しかし、世に柳生神陰流と云われた天下の剣のことだが、その稽古の足さばきを
みていると、どこかお能を想起させるものがある。そういえば、神陰流は抜かざる
の剣を求めたというし、やはり王者の
剣と いう
いう べきだろうか?
べきだろうか?
とすれば、あの劇画“子連れ狼”
で、元・公儀介錯人と敵対する柳生
烈堂(十兵衛の弟)の必殺剣は、
きっと、邪剣だったのだろう。
注) 後日談ですが、(芳徳寺の)ご住職のお話では、烈堂は幼いころに佛門に
帰依しており、あの劇画は根拠のない、単に、劇画にしか過ぎないことが
分かった。
そういえば、烈堂の“れつ”という字も違っている。
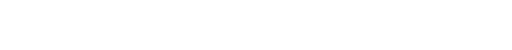
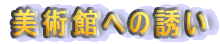 ―松伯美術館―
―松伯美術館―
このところ、木瓜の木に、うぐいすがつがいで(?)連日のようにやってきます。梅の
木と間違えているのかな? いつも、いつも ひげを剃りながら眺めています。朝の日課
のひとつ(?)ともなりました。
私の住むこの学園前には、それぞれに個性のある、
3つの美術館があります。順次ご紹介させていただき
ます。その第1回目として“松伯美術館”を。
拙宅からなら、徒歩で、10分以内のところにあり
ます。奈良県立公園の真っ只中に建っています。
交通はといえば、近鉄・学園前駅から、バスで、約
6〜7分のところです。バスは頻繁にあります(170
円? 奈良交通バスはとにかく高い! 奈良県下を独占
していて、したい放題をしている? 大渕橋下車)
さて、当の美術館ですが、もともとはと言えば、近鉄の社長だった故・佐伯 勇さん(元・
大商の会頭でもあった。)の私邸で、お亡くなりになられてから近鉄が買い上げたもの?
前面には大きな池(即ち、大渕池。もともとは佐伯さんの持ち池? 県に寄贈された?
写真参照)があり、館の敷地そのものも結構広大です。
ここには、日本画壇の重鎮のお一人でもあった故・上村松園、松篁、淳之さんの三代にわ
たる画業等(作品、草稿、写生、美術資料の収集と保管な
ど)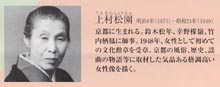 が、ほぼ、常設されています。
が、ほぼ、常設されています。
初代の松園さん(女性。当時は飛んでおられた女性?)
は、その頃には、確か、京にお住まいだったかとおもいます
が… そのご子息の松篁さんも、先年、お亡くなりになられ
ました。が、お孫さんの淳之さんはもちろんご健在で、拙宅
からすると、美術館とは反対の方向で、そうは遠くないとこ
ろにお住まいになっておられます。
既にお分かりのように、“松伯”の名の由来は、松園さん、松篁さん両画伯の“松”と、
そして、佐伯さんの“伯”とを合わされました。なお、実際には、さらに複雑な由来があり
ますが、省略させて戴きます。
桜の季節には、ここの“しだれ桜”の大老木は広く知られているところです。結構多くの
人たちが、美術館には入らず、その桜だけを楽しみに行かれるとか? 土地の方なら、うま
く、入れるのです。しかし、館内にも、鑑るべきものが多く、抱き合わせにされることを
心からお勧めします。
実は、実はです。それよりもスゴイものが、ここには、もう1つあります。それは、何を
隠そう、“花水木”の大木です。それも滅多にはお目にかかれないような大大木で、それは
それで、見事と言うしか表現の仕様がありません。
花は紅花の方です。時期的に言うなら、しだれ桜が終わってからかな? 案外と、こちら
の方は、知られていません。知る人のみぞ知るという程度? 一見には十二分に値します。
そのときにも、是非、美術館の展示品との抱き合わせ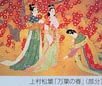 で… そのくら
で… そのくら
い値打ちのある展示が常になされていますから。
さらに、お疲れになられた方には、これぞ学園前ならでは…という
茶店(サテン、梨風庵)も近くにあります。館から、徒歩でも、
わずかな距離です。
その大渕池をも眺めながら、ゆっくりと、お茶が楽しめる? でも、
少しお値段が高いかな? それに少々、カッコ、つけすぎ? そこの
ところはお好みで…
注) 1、右の、松篁さんの、作品『万葉の春』は著作権との絡みがあり、故意にぼやか
せています。作品の良し悪しは、実物にて、ご評価下さい。
2、これは、02.4.24現在の、情報です。
3、展覧会のご案内
5月21日(火)〜6月30日(日)
上村松篁『額田女王』挿絵展
7月9日(火)〜9月23日(月・祝)
上村松園・松篁・淳之展―美の系譜―
4、詳細のお問い合わせは : TEL(0742)41−6666 に…