滝 坂 の 道
春日石仏群
峠の茶屋
柳生街道は、歩いてみなければ、おもしろさ
も良さも分からない道である。昭和の初め頃ま
では柳生の人たちは、奈良まで、1日1往復し
たというが、楽しむには無理である。
特にここが起点というわけでもないが、俗に
滝坂の道とよばれる道がある。滝がかかる谷川
沿いの坂道という意味でもあろうが、味のある
固有名詞ではある。そして、その名のとおり、
谷川は次第に急流となり、道はどんどんと登り
となる。
滝坂の道は、やがて、石だたみの道となる。
それも、登りで続く。石は、大きなものを使わず、
丹念に敷きつめてある。無数の足によって踏み
固められた石だたみである。柳生十兵衛や荒
木又右衛門らの足跡もあることだろう。そこに落
葉がつもり、露が濡らしていることもある。もう、
こんな道は、わが国でも数少ないのではないかとおもわれる。
こうして、街道は春日奥山の原始林のなかを登り、谷川が清冽な音をたてて流
れている。あたかも、自然の下を、こっそりと潜っている道という感じだ。
また、滝坂の道は登るにつれて、辺りには次々と石ぼとけが現れる。春日石仏
群である。
大和の三大石仏の宝庫の一つに春日石仏群がある。
柳生街道は滝坂の道沿いにもいくつかの傑作が点在
する。寝佛(ころがり落ちたもの) 朝日観音と云われる
弥勒仏、三体地蔵磨崖佛(室町期)などがそれである。
なかでも、小高い崖壁には夕日観音と云われる弥勒
磨崖佛(鎌倉中期)の秀作が隠れている。夕日を受ける
と美しく輝くのでこんな俗称が生まれたということなのだ
が、その呼び名がしゃれている。
また、街道からは少し逸れた地獄谷・聖人窟にも古い
石仏が多く、石仏めぐりだけでもたっぷりと一日はかかる。
彼らは、みんな、古拙の美をもっている。
さらには、滝坂の道を登ると三叉路にでるが、そこには大きなお地蔵さまが親愛
なる表情で立っている。首が切れているのは、荒木又右衛門が、試し斬りにしたか
らだという伝説が残っていて、いかにも柳生街道らしい。
その首切り地蔵から道を左にとると、いったんはドライブウェイにでて、すぐにまた
山道に入る。そして、峠の茶屋の前にと出る。
かって、柳生街道に往来者が多かった頃、
峠の茶屋では必ずといっていいほど弁当を
つかったり、或はお酒を飲って元気をつけ
たりして、常に満員、盛況だったと云われて
いる。なかには、武芸帳を、飲み代のカタ
に置いていった武芸者もいたかもしれない。
そういえば、峠の茶屋の鴨居には槍や古
風な鉄砲などがかかっており、武芸者の持っ
ていたらしい鉄扇やら、神道無念流の極意武芸帳やらも伝わっているとかいうことである。
峠の茶屋を下ると、民家の美しい村落に入り、竜吐水という昔のポンプも見かけた。が、
今はもう見られないかもしれない。奈良市中からほんのわずかな所にこんな落着いた、
静かな村が存在していることに不思議な気さえする。街道が廃れるとともに、きっと、村は
置き忘れられたのだろう。
峠からは車の通れるようないい道もついているのに、車どころか、シーズン中の観光客
以外にはひとにも殆ど出会わない。
なお、ここ・誓多林峠の集落辺りで、私は春ともなればワラビ採りを楽しむこととしている。
また、この集落から、大慈仙を経て、忍辱山・円成寺に至るが次の機会にお話したい。
 “雑草風・古寺巡礼”
周囲の幾人かの方から、前々より “雑草風・古寺巡礼” なる
“雑草風・古寺巡礼”
周囲の幾人かの方から、前々より “雑草風・古寺巡礼” なる
ものを、HP上で、書いては… というご要望がありました。
しかし、それでは、あの天下の和辻哲郎さんに余りにも申し訳ない
し、恥ずかしいし… とおもっています。
と、いうことを、さるご要望された一人の
奥さんにお答えしたところ、「田部さん、和辻
さんって、一体、誰?」と言われ、唖然とした
ことがあります。
私たち(少なくとも、私)は、古寺巡礼=和辻
哲郎と、一体化してとらえていました。
しかし、どうやら、今では古寺巡礼という
連立単語は、既にひもつきではなく、独立した
言葉として独り歩きしているようですね。そう
いえば、瀬戸内寂聴さんの古寺巡礼といったものも、確かにありました
よね。
それはそれとして、私は、既に<庭ものがたりシリーズ>などで、
まだホンの一部ではありますが、古寺などにも触れてはいます。
 過去には、私は <古美術研究会> などにも
過去には、私は <古美術研究会> などにも
参画しており、もし書こうとおもえば、書け
なくもないのはないのですが…
( H14.春 )
ご参考 )
右上の写真は、春の
不退寺(奈良市)
左の写真は、(南山城の)
当尾の里の石仏



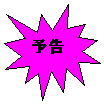

 過去には、私は <古美術研究会> などにも
過去には、私は <古美術研究会> などにも