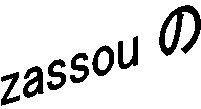
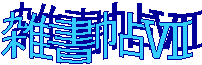
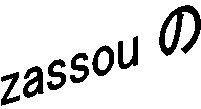
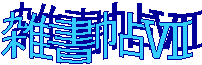
★ 朝は ディリー
から… ★
![]() 砂の男(?) 浜村温泉(いなば温泉郷、 *** )
砂の男(?) 浜村温泉(いなば温泉郷、 *** )
湯の旅の愉しみとは、いつでも好きな時に、何度でも大きな湯槽に浸かれるということに尽きるように
おもう。
ということは、早立ちや、夜遅くに宿に着く人たちの気が知れないということにもなる。とりわけ、温泉の
場合には、連泊がよろしい。
宿に着いたら、早速、浴衣に着がえる。大浴場の大きな窓越しに海や、川、湖が観えたらこの上はない。
たとえ観えなくても、鄙びた山の湯の、岩風呂などでも結構愉しいという方がおられたが、それも、全くその
通りである。
しかるのちに、酒肴などが運ばれ、親しい仲間らとゆっくりと飲む… まことに結構なことではある。もっとも、
私は、一人旅の大好きな人間でもあるが…
しかし、昨今はというと、旅館の従業員の労働条件などにも大きな理由があるのであろうか、
全てに、慌ただしくなったきた。また一方、客の方も、何やらやたらとセカセカとしている。
味気ないことは、この上ない!![]()
先だって、PCネットサークル・しじゅうからの toyochu さんが、「近頃湧いた湯の殆どは、
あれは真の温泉ではなく、“ 温かい井戸水 ”に過ぎない…」というような意味のことをおっ
しゃっておられたが、実は、私も全く同感なのである。
また、私は、《 本物の温泉 》 《 偽物の温泉 》という言葉をよく使うが、これも言い換えれば、
《 昔からのビール(即ち、純正ビア) 》と《 新しいお酒・発泡ビア 》との差とも言えるかな?
いやいや、それでは、発泡ビアに余りにも悪い? 何故なら、その(即ち、ビアの)落差は少ないが、
温泉の落差は余りにも、大きい(?)から… そういえば、toyochu さんも、同じように感じておられたなぁ~
それでは、今回は、山陰では随一の湯量を誇っていると云われている《 本物の温泉 》のひとつ・浜村温泉
をご紹介しよう。
浜村では、いくつもの源泉を持つ宿が、多いとか。お湯は、食塩泉とラジウム泉との、2種類があり、泉温
は51~69℃。泉質の効能としては、神経痛、関節痛、五十肩、リューマチ、うちみ、胃腸病、婦人病などが、
あげられている。
宿によっては、広い浴槽から、源泉の湯があふれ出している。冷えた身体をあたためて、露天風呂にも
浸かる… 雪も多い山陰のこと、冬ともなれば、湯煙の向こうで木々の梢からその雪がポトンと落ちる。
浜村も、私の、もっとも好きな温泉のひとつでもある。湯量が多いためか、プール式の、大浴場のある
旅館もあるとか。少し贅沢かな? 限りあるお湯を大切に、かな?…
先述の如く、雪も多い山陰では、空から粉雪が舞っている。国道9号線の<
魚見台 >に立つと、目の前
には、日本海が拡がっている。夏の静かな海とは違って、荒々しい白波が打ち寄せる。晴れた日には、遠く、
但馬海岸まで観えるというが、その日は、生憎と海と空との境目が分からないくらいぼんやりとしていた。
しかし、ここ・浜村温泉は、良質の海岸にも恵まれていて、夏の海水浴にもお勧めできる。遠浅でもある。
普段はのんびりとして、極めて、素朴な町も、季節が冬場ともなると、カニ・カニ・カニ…の観光客で大賑
わいをする。もちろん、山陰だから、松葉ガニと呼ばれている。
なお、今回の《 浜村温泉 》は、鳥取県の、気高郡に位置しており、私が初めてこの温泉を尋ねたのは、
もう、30年くらいも昔のことである。その折のお話に、最近の情報を、少し添えているだけだ。
浜村を、一口で言ってしまえば、《 砂丘のかげの温泉 》と言える。これは、鳥取県の湯に、相応しい。
かって、遠藤周作さんや阿川弘之さんらと共に、第3の新人と呼ばれたおひとりに安部公房さんという作家
がおられる。私の大好きな作家のおひとりでもある。
その安部さんの代表作のひとつに 『 砂の女 』 という作品がある。演技派女優の岸田今日子さんで映画化
もなされたが、まさに、その舞台を想わされる。
しかし、その時の砂丘は、鳥取県下が大晦日としては7年ぶりの大雪とかに見舞われていて、雪丘と呼ぶに
相応しい様相を呈していたが…
なお、JRの山陰本線・浜村駅前の一帯が、もう温泉街となっており、交通の便に関してはすこぶる良い。
幼児でも、大国主命と因幡の白兎と言えば、知っている伝説であるが、その話の舞台ともなった白兎(
はくと)海岸も、ここからは、近い。
また、全国的に拡がっている民謡・貝がら節は、この地で誕生した。かって、この地で、盛んだったホタテ
貝漁の苦しさを謡ったものである。いわば、漁師の、櫓こぎうたでもある。過酷な労働に耐えに耐えて、なおも、
働かねばならなかった海の男の哀愁が切々と伝わってくる。
また、後述の国民宿舎・貝がら荘の名も、この民謡に由来している。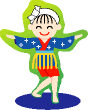
なお、私は、ここでは宿舎をその貝がら荘に求めた(まだ若かった当時は、懐が、
極めて淋しかった所為もあったが…)
時節柄、カニがなくては山陰の旅は始まらない…と勝手なことをおもって、オーダー
を入れた。
あの、カニの淡白な味わいは捨て難い。カニすきなど、いろいろな、好みの食べ方
はあるが、私は、三杯酢でやるのが、今でも、一番好きである。雄ガニが一匹つく(
その当時は、カニも、さしたる贅沢ではなかった…)と、その頃なら、軽くとは言わない
が、それでも、一升はいけたかなぁ~
ところが、先述の如く数日に渡って海は時化ていて、生憎と冷凍ものしか用意することができなかった。
宿の支配人さんからのお答えは「その冷凍ものを、お客さんに、おだしする訳にはいかない。」というすげ
ないものでしたね。
そこで、PHとして出されたのがバイ貝の煮つけで、その場は我慢を強いられた。カニと、バイ貝ですよ…
しかし、その当時にしても少ない、宿舎の姿勢に大変感心した記憶がある。それも
あってか、バイ貝の味付けにも、天下一品と言っても過言ではないものがあったなぁ~
当時名の知れた(?)雑誌『 酒 』の編集長だった佐々木久子さんは「何が美味
いったって、地酒なら、クィーン(女王)に限る…」というようなことをその誌上で
おっしゃっておられた。
たまたま、そのクィーンが、この地方のお酒で、当時は、まだ地酒も、焼酎もさほど
にはひとの心を惹かない時代ではありましたが…
という訳で、早速、酒屋さんに飛び込んで、そのクィーンなる地酒を所望した。宿で、
睡眠薬代わりにでも、飲んでみようかともおもって…
ところがあにはからんや、そこのご主人にあっさりと、「そんな酒は知らない… うちは、
灘と伏見のお酒が主流だ。」と自慢げに言われてしまい、月桂冠と、白鶴とを勧められた。もちろん、即、
2軒目を探しはしましたが…
従って、私にとっては、クィーンはいまだに幻のお酒なのである。
[ インフォメーション ]
気高町産業振興課 ℡ 0857(82)3155
または気高町観光協会 ℡ 0857(82)0829
![]() さて、真実は?? 湯抱(ゆがかい)温泉(島根県、 *** )
さて、真実は?? 湯抱(ゆがかい)温泉(島根県、 *** )
湯抱温泉。 知っている人は、極めて、稀であろう。
しかし、実は、古~い古~い湯場である。
湯抱という少し変わった名前を ユガカイ と読むのは、恐らくは、湯(ユ)ガ峡(カイ)から出たのであろうと
いうことのようだ。行ってみられるとよく分かるが、それほどに、典型的な谷間の、小平地の湯場である。
江ノ川(別称、中国太郎)の支流、尻無川のさらに支流、女良谷川の小流に臨んだ、小さな盆地に
そこはある。
国鉄(現JR)・太田市駅から、国鉄バスで、約50分(湯抱温泉口下車) 国鉄・三江北線の粕淵駅から
なら、同バスで約15分(下車は同じ…) 広島方面(三次 -みよし-
街道)から、中国山地を経て、来ら
れる来訪者も多い。
また、三瓶温泉(S34年までは志学温泉。三瓶の四岳をもじったものであろう。)からのバス便もある(乗り
継ぎを要するが…) 実は、帰路は、このコースをとったが、時刻表の関係で、タクシーとの乗り継ぎとなった。
従って、大枚を、はたく結果ともなった。

なお、俗に“ 霧の三瓶 ”と云われる三瓶山周辺も、幾度尋ねても飽か
ない、素晴らしい大観光地・温泉などではあるが、また後日に残しておこう!
下車後は、せばまった女良谷川に沿って、500メートルもゆくと急に開けて
温泉場が現われる。
旅館以外には、余り、建物も目立たない。温泉地のなかの女良谷川はささ
やかな小川並みとなって、季節ともなれば、川岸の櫻並木が、大変美しいと
いう。しかし、私は、その直前の3月に訪れた。
橋をはさんで北側にもっとも大きな日之出旅館(私は、ここに、泊めて頂いた。) また、南側には鴨山、
中村、広島屋などの宿があり、まともな土産もの屋さんひとつない、静かな環境ではある。
お湯は色のついた(瞬間的に、兵庫県・神戸市の、有馬温泉を想った。)鉱泉で、含・炭酸弱食塩泉で、
泉温は20~36℃。微温泉を湧かしているようである。
なお、お湯は、各旅館によって多少泉質を異にしているらしい。
一般的には、神経痛やリウマチ、胃腸の名湯として聞こえているらしいが、とにかく気分がよくて、古典的で
あって、また湯治場的でもある。
なお、この知られざる湯が多少とも知られるようになったのは、かって、あの斎藤茂吉が「万葉の代表的
歌人・柿本人麻呂が死んだのは、ここの、鴨山だ。」と結論し、議論を巻き起こしてからのことである。
その鴨山は、温泉場の、200メートルほどのところにある。
あの、私の大好きな人麻呂が、ここを、終焉の地として選んだ背景には、万葉の当時に既に、湯抱のお湯
があったことを物語っていはしないだろうか? 私は、そう、推察した。
この湯抱温泉を訪れるに当っての、私の、最大の関心事でもあった。
もしそうなら、ここのお湯は、温泉史的にみても極めて貴重なお湯という
ことにもなってくるのだが…
柿本人麻呂、石見国に在りて臨死(みまからむ)とするとき、自ら傷みて
作れる歌 『 鴨山の 磐根(いわね)し纏(ま)ける 吾をかも 知らにと妹が
待ちつつあらむ 』
そして、茂吉の歌碑が、その鴨山に近い公園の丘に建っている。『 人麻呂
が つひの命を 終りたる 鴨山をしも ここと定めむ 』
その側には、アララギの若木が…
万葉の歌聖と、昭和の大歌人の魂は、薄明の霧のなかで、相かたらい
ながら、その空間を漂っているかのようにみえた…
しかし、近年に至って、異色の哲学者・梅原猛氏はその代表的な著作のなかで人麻呂刑死説を唱え、
茂吉説と真っ向から対立している。
果たして、その真実とは??… だから、歴史も、おもしろい…
[ インフォメーション ]
邑智町役場産業開発課 ℡ 0855(75)1211
注) 実は、私がここを訪れてから、既に30年くらいになります。そして、それ以降は、ここを尋ねた
ことはありません。だから、この文章は、30年前に作成したものを全文そのままに掲載させて頂い
ております。例えば、国鉄という表現が、それを如実に物語っています。
従って、もしも関心を示されて、お出でになられる方があれば、十分に事前調査の上でお出でに
なって下さいね。
但し、この湯抱温泉は、今も立派に存在しているということのみを付記させて頂きます。
また、人麻呂終焉の地についても、今なお不明の存在として残っています。
| 黒 薙 温 泉 へ | 川 湯 温 泉 へ | いい湯だなぁ~ へ | 吉野温泉元湯 へ |
| 小 浜 温 泉 へ | 草 津 温 泉 へ | 温泉があぶない!へ | カニの温泉宿 へ |
| 温泉一口メモ へ | 吉 良 温 泉 へ | いろいろな温泉 へ | 目次のみのページ |
| - 初詣ハイキング - |
| 学生時代から35(才)くらいにかけては、毎年お正月ともなると、石上神社( 大和・天理市)から三輪神社(同じく大和・桜井市)にかけての大和青垣山の山裾 を縫うみちを歩いていましたね。 そのみちは、俗に“山辺のみち(または万葉のみ 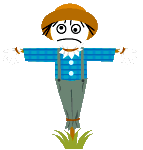 ち)”と云われて ち)”と云われているみちの、一部です。 歴史にも登場するような大きな古墳や、環濠集落などを横目に見て、 点在する多くの史跡にも時に足をとめ、また時には万葉の歌人を偲ん だりして… そして、みかん畑を横切り… それは、丸1日がかりでしたね。 私たちは、当時、それを《初詣ハイキング》と名付けていました。 今でも、そんなもの好きなことをする人たちは、いるのかな? でも、私たちは、15年くらいは続いたかなぁ~ 久しぶりに、また、歩いてみたい気持ちにもなってきましたね。 注) この山辺の道は、飛鳥(明日香村)と奈良(市)とを結ぶ、日本最古の国道2号 線とも位置づけてもいいものです。 ちなみに、日本最古の国道1号線は、同じ飛鳥から竹之内街道や、河内平野を横 切って、難波京(大阪市)に至る道です。 そして、国道3号線はというと、その難波京と平城京(奈良市)とを暗峠(くら がりとうげ、生駒山系…)越えをして結んでいる旧奈良街道のひとつ(これが、難 波京とを結ぶ、最短距離です。)だとおもいたい。 そうすると、もうお分かりのように、“現・明日香村”と、“現・奈良市”“現・ 大阪市”とは、丁度、ほぼ二等辺三角形を形成していることとなります。 そして、その二等辺三角形の内側とその周辺とで、大輪の文化の花も開きました。 それらは、やがて、『 あをによし ならのみやこは …… いまさかりなり 』 あの、絢爛豪華を誇った天平文化へ… と結実していきました。 |
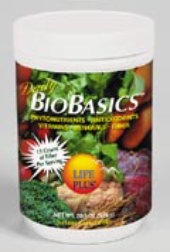
朝は ディリー から…
結局、バランスが、一番大切です。
始められる方は、野菜不足と腸内の環境
整備から、始めましょうよ!!
![]() 暗 や み で み た !
暗 や み で み た !
小屋を出る。
深夜の山道である。暗い…
一歩一歩、足もとを確かめ、踏みしめながら登る。
盛夏だというのにやけに肌寒い。
腰に巻きつけたセーターを着る。
小屋の灯が遠くなった。
まっくらである。立ちどまる。
かすかに草の匂いがする。む、土の匂いもするようだ。
精神を集中させる。
次第にまっくらだった周囲がほの見えてくる。
岩にそっと腰を下ろし、空を見上げ驚倒する。
濃紺の夜空はまっ暗ではなかった !
それどころか、輝く星くずの饗宴だ。
身体が冷えるまで見惚れる。 
原始の人間にもどる感覚を、暗やみでみた。

- 上の縦走の頃などに作った駄作(数句)もメモされていました。
これらも、恥ずかしながら、併せて公開させて頂きます。 -
“ 荒海を 渡りし雪の 乱舞かな ”
- 若かりし頃、お正月には、雪が降り、積もり、静かな心なごむ山陰の自然の
なかで、憩うことも多かった。往く年のことは全て記憶の彼方へと去り、新
しい年の神秘さに浸ったものです。山陰の、日本海を越えてくる異国の雪は
荒々しく、そして冷たく、しかしどこかで楽しかった思い出もあるように、
いつまでも、降り続いていましたね。その折に、拙いながらも、1句を… -
“ 南天に 銀の糸ひく 流れ星 ”
“ 独活の花 大山(おやま)曇れど 明日は発 ”
- 山のなかで車の急ブレーキの音が響き、抵抗するかのように蝉の声が森林から
湧きあがる。たっぷりと一週間は山のなかで過ごしてきて、時には自己の存在
までも忘れてしまう。いづれは土に還る肉体、その魂には、一体何処へ行けば
いいと言えばいいのか。その土も荒れ果てて、雑草が繁り、誰も省みなくなっ
た時に、それは、初めて真実の土となる。そうおもえば、私の心は、都会に帰
ってきても、まだ山のなかをさ迷っている。すべての絆を断ち切って、静かに
眠ることができるときまで、その土を求めて放浪をしつづけるのかもしれない…
そんな心境のなかで、1句を… -
“ 山の柿 倖せ待てと 言えば哭く ”
“ 熟し柿 突っつく鳥や 秋の暮 ”
![]()
![]() 殴 り 書 き !! より
殴 り 書 き !! より
☆ 最近、昔のものを、整理をしていて、大変に古~い、古~いメモ書きを
見つけました。まさに、殴り書き!!と言っても、いいようなものです。
実は、上のものも、そうです。とても懐かしくおもっております。
そこで、そのホンの一部を、殆ど手直しナシで公開させて頂きます。
というのも、その辺りは、今もまだ当時と余り変わってはいないのでは?
とおもうからに他なりません。
その辺りとは、即ち、休暇村のある蒜山(ひるぜん)高原から、同じく
休暇村のある大山鏡ヶ成(かがみがなる)への辺りを指します。
それでは、以下にて…… ☆
「 …… 鏡ヶ成高原の原始林に凄い雷雨が過ぎ去ったあと、空が急に輝いて、ふと顔を上げると、
あっと息をのむような無数の星が 出ていました。それは美しいというよりも、恐怖に満ち満ちた
出ていました。それは美しいというよりも、恐怖に満ち満ちた
瞬間でもありましたね。もしもこの星の群れが落下でもしてきたら、地上
のもの全てが、埋没してしまいそうなすさまじいばかりの光景でした。
何らのわけもなく叫びだしたくなるようなこの孤独感は、一体、どう
したということなのだ! 時間をさえ失ってしまった魂は、いま、この
身体から離れていってしまいそうだ。ひとりの無力な人間は、悲哀にも
似た気持を抱いて、ただ蹲っているばかりだった。
★ ★
ザックの重みがやけに肩にくいこんでくる。毎年、荷物が、重く感じられるようになった。
少々無理だったかもしれないが、家を出るとき計ったら、38kgあった。その前の年は、天幕・
寝袋・ショベル等もかついでも、45kg以上もあったのに、炎天下の同じ山を越したのだ。
山から清水が湧いているところで小休止する。とうとう、情けないことだが、3kgの米の袋
を友人に持ってもらうことにした。
さぁ~ 出発、真青な空には、白~い白~い真夏の雲が一片浮かんでいた。
★ ★
朝から、もう、七時間も歩いている。シャツはしぼったらポタポタと汗が
水のように落ちる。うっかりと空を仰いで、太陽が、眼にでも入ろうもの
ならそのままぶっ倒れそうな暑さだ。
〔 中 略 〕
やがて残照の西の空に 伯耆・大山(だいせん) の姿がちょっぴり眺められるころ、重たい
靴をひきずって高原を降りてゆく。重たいザックもかついで、汗をいっぱい流しながら、暑~い、
暑~い夏空の下をバカみたいに歩いてゆく。
★ ★
人間(ひと)は、何故、山に登るのだろうか ?
苦しみを越えて、一つの目的を、果たすために… あるいは、自分の、力の限界を試すため
に… そして、時には、心の悩みからエスケープするために… その心の安らぎを求めて…
何故、このような無償の行為に、どえらい体力を消耗しようとするのか。
笑うなかれ、無償の行為に全力を尽くすことの美しさを。 …… 」
| ページのTOP へ | なんせんす所感 へ | pdf化ファイルの目次 へ | 語ならべ1 へ | 次 へ |