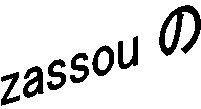
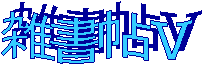
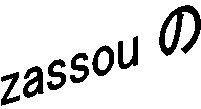
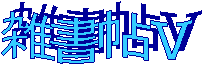
![]() 維新前後の人たち 1
維新前後の人たち 1
エッセイストとでも言えばいいのかな? 故・白洲正子さんという方がおられます。私の拙いHPの
中の ~ zassou の雑書帖Ⅰ~ からでも、若干ではありますが、その横顔を見て頂くこともできます。
その正子さんの祖父は橋口さんといい、のちに樺山家に養子に入り資紀と称されました。生粋の
薩摩隼人です。
その資紀さんは、次のような、興味あることを言っておられます。
「 我々のことを維新の元勲だとか何だとか世間では云っているが、ほんとうに偉い人たちはみな
早くに死んでしまった。残ったのはカスばかりだ。 」と…
実は、このことばには、私が30年余言い続けてきたことと奇しくも一致する側面があります。
例えば、その例を長州にとってみても、将来を嘱望された吉田松陰や、高杉晋作、久坂玄瑞、
大村益次郎などは早世し、小物の、まさにカスに相応しい伊藤博文や、山県有朋などが明治政府
を支えました。
その中でも、とりわけ、山県に至ってはあの戊辰戦争の中でも最激戦と云われた“ 北越戦争 ”に
於いて官軍の指揮をとり、有能な河井継之助(長岡藩家老。武装中立の夢をもっていた。司馬さん
の作品・峠に詳しい。)に絶命を強いるなど、カスの中のカスだとさえおもっています。
今でも多くの史家の間では、明治政府初期の二大失政として、この河井
継之助と、元老中・小栗忠順を死に至らしめたことだとも云われています。
さて、その河井継之助のことですが、反面戦さにも強い男だったことが、後に
大きな、大きな悲劇を生むことともなりました。
しかし、それらのカスたちが支えても、明治政府はそれでもあれだけのことをやってのけました。
考えてはいけないことなのですが、もしもあの松陰らが… とおもってしまうこともあります。
となると、小泉さんをはじめ今日の日本の政治家は、明治の政治家からみてもカスのカスの……
政治家たちなのかな? 或いは、アメリカの、ブッシュだって…?? ( H15 春 )
追記 ) 上の文に対して、あるお方が、次のような一文を寄越して下さいました。即ち、
『 河合継之助は、司馬遼太郎の「峠」を読みました。 彼の気持は分かるし、山県狂介(
注、のちの有朋)の横暴さも常軌を逸していると思いましたが、河合継之助はなぜ我慢
ができなかったのかと感じました。元老中・小栗忠順を斬首にしたことは、私がワイがや
のMLにも書きましたが、日本海海戦に勝ち、日本繁栄の基となった浦賀のドックを
作った人を、惜しいことをしたと感じました。 私は、そのドックは何度か訪れているだけ
に残念に思いました。 』
この文に対してまた、私も、次の一文をお返しさせて頂きました。即ち、
『 河井継之助について、少しだけ… おっしゃることは、十分に、理解できます。継之助
の行動には、いくつかの、矛盾点も指摘されていますね。例えば、時代の流れが読めて
いたにもかかわらず、政府軍への戦いを挑み長岡を戦火にまみれさせた点などはその
最たるものでしょう。多くの史家が云われるように 「
もう10年早く、またはもう10年遅く
生まれてきて欲しかった人物 」 と言えるかもしれませんね。
★ 「 英雄というのは、時と置きどころを天が誤ると、天災のような害を
することがあるらしい。 」 ( 司馬遼太郎著 ・ 英雄児より ) 』
![]() 維新前後の人たち 2
維新前後の人たち 2
津本陽という作家がおられます。その作品『 薩南示現流 』には、次のような、逸話のひとつが
載っています。
示現流(過去には自顕流と云った。この改名にも深い仔細があります。但し、省略します。)という
のは、薩摩の島津藩で、おこなわれていた剣道です。
その使い手のひとりである指宿藤次郎が、京の祇園の石段下で、見廻組に殺されました。もちろん、
幕末のことです。
その時、前田某という、若侍が同行していましたが、彼はいち早く遁走してしまいました。指宿は
五人の敵を倒しましたが、下駄の鼻緒が切れて転倒し、無念の最後を遂げました。
その葬儀の場に、橋口覚之進という、気性の激しい若侍がいて、焼香の時がきても棺の蓋を
覆わず、指宿の死顔を灯火のもとにさらしていました。
彼は、参列者のなかから、前田を呼んでこう言いました。 「お前が一番焼香じゃ。さきィ拝め!」
ただならぬ気配に、前田は、おそるおそる前へ進み出て焼香し、指宿の死体の上にうなだれ
ました。
その時、橋口は、腰刀を抜き一刀のもとに前田の首を斬り落としました。首は、ひとたまりもなく、
棺のなかにポトンと落ちてしまいました。 「こいでよか。蓋をせい!」 ……
ホントのお葬式は、そこから、始まったのではないでしょうか?
いやはや、何とも野蛮な、凄まじいお話ではありますね。
しかし、橋口にしても、前田にしても、そうしなければならない理由があった? …
但し、ここから先を、ホントにご理解したい方のみ、またご納得したい方のみ、津本さん
の作品を読まれるなり、示現流や、薩摩隼人・薩摩藩などの勉強でもなさって下さい。
また、司馬遼太郎さんの作品『 翔ぶが如く 』なども、大いにご参考になるかもしれ
ません。
そうすれば、この野蛮な、何とも凄まじいお話も、或いはご理解も、またご納得もできるの
では? …
なお、ここに登場した、気性の激しい橋口覚之進なる若侍こそ、先の(1の) お話に出てきた橋口
さん(即ち、白洲正子さんの祖父の若き日の姿です。のちに、樺山家に養子に入り、資紀と称され
ました。)そのひとです。
また、覚之進の兄・伝蔵さんは、あの余りにも有名な、伏見の“ 寺田屋騒動 ”において殺されて
しまいました。血気に逸り、討幕を企てた張本人のひとりが伝蔵さんだったという訳です。
なお、祖父の資紀さんなりのことについては、白洲(正子)さんの自伝を読まれても、かなり、詳しく
お分かりになられるかともおもいます。 ( H15 春 )
![]() 蛙の子は蛙ではない!
蛙の子は蛙ではない!
よく世間では 「蛙の子は蛙だ。」 とか云います。歌舞伎の役者や映画俳優、近頃では、政治家
などに対しても…よく云われていますね。
しかし、私は、昔から 「蛙の子は蛙ではない!」 というのが実は自論なのです。
例えとしては、些か、悪いかもしれませんが… 例えば、ここに、1人の“ やくざ ”がいるとします。
その親もやくざでした。しかし、その1人のやくざがやくざであるのは、その親がやくざであったから
では決してありません。世に、やくざな血というものは、存在しません。そのやくざがやくざである
のは、そのやくざが、やくざな行いをするから以外の何物でもありません。
このことを、あの、余りにも有名な命題 「存在は本質に先立つ」 をもって説明しようとした人が
いました。 実存哲学の第一人者・サルトル そのひとです。
ジャン・ポール・サルトルは、このようにして、自己の哲学(即ち、実存の哲学)を展開せしめ、
一世を風靡した哲学者のひとりではあります。
私たち仲間も、20~35歳くらいまでは、その実存主義にかぶれたものです。即ち、サルトルは
もとより、ハイデカ-やヤスパース、カミュなどを貪り読みましたね。
特に、 カミュ は、小説家として著名( その著作にはペストや、異邦人などがある。)なのですが、
私は、むしろ彼の哲学書の方により惹かれました。
彼の、古代神話に取材した 『 シジフォスの神話 』 は、神の掟に背き、神によって、シジフォス
に課せられた果てしのない使役を通して、自己の哲学を展開せしめました。

さて、話は戻りますが、歌舞伎役者が歌舞伎役者として世間に認められるのは、
彼が血のにじむような努力をされた結果以外の何ものでもありません。従って、
決して、「蛙の子だから、蛙になれた。」 訳ではないのです。
それが証拠(?)には (見た目には、一応、蛙にはなっているが…) 昨今の、
一部かもしれませんが、二世政治家の余りのお粗末さには目を覆いたくなる
ものもありますね(その一例、小渕元・総理の娘…)
これは、政治家としてのしなければならない自己研鑚をしていないからだ、とおも
います。或はまた、お金ででも蛙になった?
話は再び戻って… 人間誰しも、ひたむきになればなるほど、その道は開けるものだとおもいます。
序でですから、私の、大好きな言葉はこの“ ひたむき ”と、やくざがでたから言うのではあり
ませんが、実は“ 極道 ”なのです。道を極める、な~んて素晴らしいことではありませんか!
そういや~、道を楽しむ、即ち“ 道楽 ”もいいなぁ~ ( H15 盛夏 )
![]() 維新前後の人たち 3
維新前後の人たち 3
久し振りにおもしろい、極めて手応えのある作品を読ませて頂きました。
《ネットサークル・しじゅうから》のかわせみさんの妹さん(平尾信子さん)が
書かれたもので、そのタイトルは 『 黒船前夜の出会い(NHKブックス)』 と
いう作品です。ノンフィクション賞も貰われており、あの故・司馬遼太郎さんも激賞
されたと いうのも十分に頷けます。
クーパー船長の率いる、アメリカの、捕鯨船は日本人漂流民22
人を救助し、鎖国中の国・日本のお江戸へ届けようとされました。
この時代、このことは 、極めて危険な行為でもあり、また大きな
、極めて危険な行為でもあり、また大きな
政治的配慮も要求される事柄ではあります。
しかし、そのとき、勇気ある、聡明な船長にはある、ひとつの
大きな大きな好奇心もありました。さてさて、その好奇心の、
結末や如何に?
もちろん、お分かりのように、このお話は実話です。
それも、あのペリーの、四隻の黒船来航に先立つこと8年、
そのおおよそのところは想像もなさってみて下さい。
やがては、そのことは、あのペリーの知るところともなり、その結果が現在の
日米交流への、大きな大きな原点へ…ともなっていきました。
微妙なテーマにもかかわらず、大変に読み易く、またうまく纏めることも
なされています。
なお、周辺の資料をも含めてよくよく取材もされており、特級の歴史秘話と
して心からご推薦致します。
付記
) 同作品は、“ しじゅから ”の蔵書のなかにも、収められています。
X氏は自社の入試試験官をとらえて、「どうだね、新入社員は君が手に負えないとおもう者だけを
採用してみては?」 と提案されました。
これは、試験官が、気に入るような学生ばかりだったら、その学生がどんなに頑張ったところで、
伸びる頂点はせいぜい試験官のレベルまで…ということなのでしょう。
それでは、会社の発展は、おぼつかない。
即ち、X氏は、「常識人である上役が、常識人の部下ばかりを、使って
いては何も 生まれては来ない。」 と言われているのです。
生まれては来ない。」 と言われているのです。
もう少し言葉をかえれば、《 落ちこぼれと云われる若者のなかにこそ
得がたき逸材がいる。 》 という意味でもありましょう。
さて、このX氏とは? 知らない人はいません、今は亡き、世界の
ホンダの創業者の、あの 本田宗一郎 そのひとです。
そのホンダが、独創的なノウハウをもって、世界制覇を遂げるに
至った背景のひとつでもありましょう。
| |
大陸から渡来された人たちが安らぎの地を願ったところから、即ち《 安宿 》が 訛って“ 飛鳥 ”に… また、今とは違って、当時は、大陸から渡来するという ことは生死をかけた決断に外なりません。その人たちの姿を天を《 飛翔する鳥 》 のイメージとしてとらえ、“ 飛鳥 ”という地名の由来に…… など、など。諸説が プンプンです。 何れにしても、“ 飛鳥の地 ”は、今でも謎が多く、また多くのロマンも 漂っています。 「 おいでやす 飛鳥へ!! 」 |