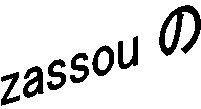
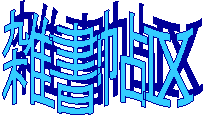
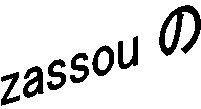
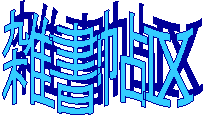
★ 朝は ディリー
から… ★
- 介護の1 へ -
- 介護の2 へ -
![]() 円空さん と 木喰上人 …
円空さん と 木喰上人 …
飛騨の高山にも久しく訪れてはいません。
その高山には確か国分寺があって、そこの大きな、大きないちょうの木は、恐らく今も健在
なことでしょうね。
そのいちょうの木に、私は、手前勝手に“おばけいちょう”と命名していました。
大木の下から見上げた真っ青な空の色が、今も、はっきりと記憶の底に残っています。
その大木も、恐らくは、黄色く色づいて来ていることでしょうね。
その国分寺の一隅には、“円空洞(?)”とか呼ばれていた、一軒のお店がありました。
さてさて、今も、まだあるのやら、 どうやら… ??
どうやら… ??
そのお店では、さすらいのお坊さんのお一人で、かつ結果的には
江戸時代の、著名な一彫刻家としても位置づけられている、あの
円空さんの模作を彫って、売っておられました。
模作だからもちろんその重量は極めて軽いものであり、もともと
が円空さんその人も極めて荒削りな鉈彫りでしたから、その模倣と
はいっても一体を彫るにかかる時間はとなると極めて短く、従って
その完成品とはいっても大変に値段の安いものでした。
それでも、私は、大いに気に入っていたものですから、訪れる度
に、多くを買って帰えり、友人らにバラ撒いていました。
さて、その円空さんですが、私の学生時代、後藤なにがしさんとか云われた一写真家に
よって、大きく、かつ広く、世に知られるところともなりました。
その後藤さんによる“円空佛の写真展”なるようなものが、確か、日経新聞だった
かな?? の後押しで、大阪の某百貨店においてもたれました。
こちらも“微笑佛”の一つとも呼ばれている、円空さんの手による佛さまがもつその
優しさや、人懐っこさ、そして100万弗とさえ言ってもいいような、あの笑み、さらには
その新鮮さ・斬新さなど… に惹かれて、今でも、生々しく記憶の底にありますね。
その円空さんは美濃のお坊さんで、哲学者でもある梅原猛さんによると、「本当の芸術
には思想がある。円空は(石川、福井、岐阜の霊場)信仰の修験者として、日本古来の、
神仏習合の思想を身につけ、それを仏像造りによって表現した。」ということになります。
その円空さんは、一説によれば、その生涯には十万体以上もの多くの彫像を刻まれたとか。
一夜の軒先を借りた宿代わりのお礼に彫っては差し上げ、また新たな旅に出られた…
日本全国尋ねなかったところはない位に、転々と…
味ある写真家・後藤さんによって日の目を見るまでには、惜しいことに、その作品の多く
はお風呂の薪代わりにもなってたゆとう煙と化したりなど… していたとか。或いは、それ
こそがまた、極めて円空さんらしいとも云えるのかな?
円空さんと言えば、もう一方、極めてよく似た漂浪の旅を続けられた、有名なお坊さんに
木喰上人がおられます。よくよく、円空さんと、対比されたりもしますね。
 彼の作品群も、一般的には、“微笑佛”と呼ばれて
彼の作品群も、一般的には、“微笑佛”と呼ばれて
います。
なお、彼の、多くの優れたその作品の中の一つでも
ある立木観音を、川西池田(大阪府下…)の奥(即ち、
猪名川の上流…)にある某お寺で拝むことも出来ます。
そこでは、また、自刻像なども、観ることが出来ま
した。
立木観音はというと大変に珍しいもので、大木に
直接刻まれた作品の、そのスケールも大きく、それは
それで、また非常にすご~い、迫力ある作品でした。
もちろん、その観音さまも、微笑んでおられましたよ。
折からの妖花・まんじゅしゃげの乱舞に、一層、
映えておられました。
なお、木喰行道の芸術は、あの柳宗悦さんによって発見されました。それから、もう、
早や100年近くにもなりつつあります。
季節が今頃ともなれば、時折、飛騨の高山は国分寺の“おばけいちょう”を想い、また
その延長線上で円空佛やら、木喰佛やらの“微笑佛”をも連想してみたりして、一人旅への
心を激しくそそられたりもしますね。
~ H16.10 ~
![]() 愛 染 さ ん …
愛 染 さ ん …
かわせみさん(HN。ネットサークル・しじゅうから…)に…
四天王寺(注、大阪市内…)界隈散策のハイライトは、私の場合なら、< 四天王寺別院・
勝鬘院…(俗には、愛染さんと、呼ばれています。) >ですね。 ![]()
愛染とは? それは、読んで字の如く、愛に染まること…
この愛染という言葉が、いつの頃からか、心に沁み入って懐かしくおもいます。
大阪の人たちは…となると、7月の夏祭り月が、ここの<愛染まつり >から始まっ
て、南の方角に位置する< 住吉まつり >で終わることを、よ~く、知っておられ
ます。実は、青年時代?までの、私自身もそのひとりではありましたが…
かっての市電、または市バスを降りて、私の過去には、何度ともなく登ったり、
降りたりしたのが、かわせみさんのおっしゃっておられる愛染坂かな?
もしもそうなら、この石段の、魅力ある坂道は、正式には(?)< 勝鬘坂 >とも
呼ばれる、大阪では私の最も大好きな坂道のひとつでもあります。
また、ここの愛染明王に相対してみると、愛染というお名前の美しさからは、
凡そ、想像も出来ないような忿怒像でしたね。
人間の男女関係とは心身無残の苦痛を包蔵してこそ、真に、愛染の名に値する愛着を…
とでもいうことなのでしょうか?
なお、このことは事実かどうかは知りませんが、ここの〔かつらの木〕は、上原謙さん、田中
絹代さんらによった、往年の名画〔愛染かつら〕(霧島昇さんとミス・コロンビア~のちの松原操
さん~による、その主題歌・旅の夜風も大流行しました。)にゆかりのものとか、どうとか??
なお、夕陽ヶ丘高女の初代教頭でもあられた、薄命の歌人・前田純孝さんは、ここ・愛染塔
の九輪にかかる秋の月を< 夕陽丘八景 >のひとつとして取り上げられておられます。
この地が夕陽ヶ丘と名づけられた経緯には、先の阿修羅さん(同・しじゅからのメンバー)の
文章にもあった、新古今の歌人・ (藤原)家隆が、詠んだところからきて
(藤原)家隆が、詠んだところからきて
いると、一般的には、云われていますね。
またさらには、近松の< 冥土の飛脚 >には、忠兵衛の封印切りの
あと大和へ落ちていく梅川忠兵衛の道行に 「 … 振り返り見る勝鬘
の、愛染様に愛敬を、祈る芝居の子供衆や、道頓堀のいろいろや、
馴れしくるわのそれぞれとは紋で憶えし提灯の、中にはかなや槌屋内、
この木瓜に打添いて、私が紋の松皮の、松の千歳を祈りしに、定めぬ
契り提灯の ……… 」 とあります。
振り返り、振り返りするふたりの目には、きっと、塔の九輪はいつまで
も、いつまでも消えなかったことでしょうね。
ふたりの愛染が、社会に、背反する結果となってしまったことへの
悲しさ、辛さ、そして苦悩…… あらぬ幻想の世界へと誘われてしまい、
ふと、目を閉じさせられてしまったこともありましたね。
こちらも、かっての名画・〔浪花の恋の物語〕…
若き日の有馬稲子さんの演じる梅川、故・中村(のちの萬屋)錦之介さんの忠兵衛に、そして
特別出演として近松役の(片岡)千恵蔵さん… 監督は、確か、内田(吐夢)さんだった? おぼ
ろげながら、憶えておりますね。とりわけ、観せてくれて、聴かせてくれた、あの人形浄瑠璃(
一般的には、文楽と、呼ばれている。)の名場面などを…
かわせみさんも、是非とも、また再訪して下さいね。
~ H16.10 ~
![]() 介 護 シ リ ー ズ - 1
介 護 シ リ ー ズ - 1
《訪問介護員(2級)養成研修会を終えて》
この6月16日付けの朝日新聞に<介護保険>=「楽(らく)」がくせもの=という
社説が載った。その要旨は次の如きものだった。
『介護サービスの利用によって高齢者が楽をすると却って障害が重症化する。介護
保険拡大が問題となっている中で、サービス提供事業者の過剰な支援を戒める。殊に
福祉用具の安易な利用をやり玉に挙げている。要支援や要介護1などの症状が比較的
軽い高齢者が、サービスを受け始めて、短期間で重くなる例が少なくない。』 また、
社説は続けて、『53才の時に脳内出血にて寝たきりを宣告された方が、介護器具に
頼らない暮らしの中でリハビリに励み、大幅な回復を得た。』と強調している。この
社説と同様の指摘は、 本研修においても、あった。
本研修においても、あった。
この社説に対し、当然、サービス提供事業者からは猛烈な反論が
出た。その筋の団体の理事は、細かいデータ(省略…)を揃えて、
『重症化については、敢えて言うなら、要介護3が最も高いの
ではなかろうか。また、50才代と70才代以降での障害の克
服を同じと考えて良いのだろうか。』などと具体的に反発をさ
れ、その締め括りとして『「おんぶにだっこで楽ちんとだろう。」
と考えることは全く筋違いであろう。社説の筆者にはノーマラ
イゼーション(注、邦語訳では“正常化”“常態化”の意…)
の意義、意味に振り返って頂きたい。その上での議論でなけれ
ば介護保険制度が危うくなる。』と憤りをもって述べておられた。
さらに、松原市の60才に近い主婦は、過去に2級過程の資格
を取られ、最近訪問介護員として仕事に従事されている。その方
から次のようなEメールが届いた。以下は本の一部だが。『私は性格的に情に流され
る方で、つい想いが入ってしまい、仕事とボランティアとが入り交ざってしまいそう
で気をつけなくてはなりません。(中略…)やはりヘルパーとしての本分は訪問介護
に尽きるとおもいます。その中で最近感じたことなのですが、贅沢になっているのは
厳しい時代を生きて来られたお年寄りにもいえることで、「ご自分で出来ることでも
甘えておられる。」ということです。介護保険では一割負担でやってもらえる手軽さ
から、利用する必要のない人でも安易に使っているということです。これでは年金や
他の社会保険と同様、近いうちに財政のパンクする状態は見えています。私たちに
とってもより厳しい現実が待っていることでしょう。(以下、略…)』 確かに、医
院の待合室は高齢者のサロン化し、健保制度は、大きな雪崩現象さえ起こしている。
以上の例は、その立場の違いこそあれ、今日の介護の現場での実態、その問題点な
どを明確に浮き彫りさせている。本研修の場でも、実習の場でも垣間見てきた。私も、
浮かび上がった問題点などを、些かも否定はしない。潰すべき課題は一つづつ丹念に
潰していかねばならない。そうしなければ、私たち全ての首が絞まってしまう。サー
ビスの利用者も心しなければならないのも厳然たる事実だ。小さな無駄の集積もバカ
には出来ない。
しかし、これらの例は、枝葉の要素であって、もっと太い幹の部分は隠れているよ
うにおもう。結局は政治や行政などのあり方に帰するようにおもう。そのことは、本
研修を受け、実習で得た貴重な体験を通し、また私自身の体験や世間の会話などを知
れば知る程にそうおもう。結局は政治や行政を中心とした複合汚染のようなものを、
既に、感じる。
「 人生いろいろ、会社もいろいろ、総理大臣もいろいろ…」と
人生いろいろ、会社もいろいろ、総理大臣もいろいろ…」と
いったレベルの政治家たち、腐り切った中央の高級官僚とその官僚
の顔色を窺って、国民の方を見ていない小役人、依然として横たわ
る縦割り行政の弊害など。こうした背景が未完の大きな幹の存在を
許し、さらに折角育てた幹をさえ腐らせようとしてはいないだろう
か。以下は本の一例ですが。『特別養護老人ホームに入所している
人が病いの床に就き、入院へ。入院先で2ヶ月後に回復したとする。
ところが、特養では、入院の1週間後に既に新しい入所者を決定し
ている。それでは、その無事回復された人は一体どこへ戻れ!とい
うのか。待っているのは地獄だけなのか。』 この例は健康保険と
介護保険との狭間での問題だが、これらは氷山の一角のようにおもう。ある実習でも、
国は、もう施設は作らないと聞いた。本研修でも、特養は、既に石油パニック並みの
行列が出来ていると聞いた。それでは、国は、ターミナル・ケアーやターミナル・ステ
ーションの問題を本当に解決できると考えているのか。
先述の如く、健保制度の雪崩現象。高率の消費税によって賄われようとしている
年金問題、それでは蛸が自らの足を食って生き延びるような構図ではないか。無策も
過ぎる。向後の介護保険制度の改正にも大きな期待は寄せられず、後退を余儀なくされ
ることだろう。本研修では、それらも、同時に示唆してくれた。 (H16.7末)
![]() 介 護 シ リ ー ズ - 2
介 護 シ リ ー ズ - 2
《姥捨て山のことなど…》
下の文章は、最近、ある老健(介護老人保健施設のこと…)の某氏からご依頼があって認めさせて頂いた
作文(400字詰めの原稿用紙・4枚の範囲内でという条件の下で…)でしか他なりません。
おもうところがあって、訪問介護員2級の研修を、受けました。老人施設での実習
なども含めて、貴重な体験の数々なども、させて頂きました。
実習でおもったところは、最大のポイントのひとつは、声がけにあるなぁ~という
ことでした。入浴介助、おむつの交換などの技術的なことも極めて大切なことではあ
りますが、それ以上に対話することの難しさとその必要性とを痛感しました。その結
果によって、対応も、的確さを増すようにもおもいます。ホントは、その辺のこと
を、認めたかったのですが、今回は敢えて別なテーマを選ぶこととしました。その
テーマとは、『ドライヤーについて』 ということです。
入浴の折に衣服の着脱などと共に、私も、ドライヤーを使って濡れた髪を乾かせて
差し上げました。そのことは、研修での同級生たちも、その多くが体験したよう
です。しかし、多くの人たちが、そのことを軽くみていて、その時間帯をあたかも
サービスのご提供における楽勝の時間帯のように受け止めていたことが、少し、気に
なりました。
なお、以下のことは、私自身のみの場合ですが…
次々と入浴の方が入って来られ、いろいろな役割が絶えず
押し寄せて来ます。即ち、一緒に湯船に浸かる、背中を流し
て差し上げる、お薬を塗ってあげたり… 従って、髪を乾か
すのに、さほどの、時間をかけておれないのが実情です。そ
こでですが、ドライヤーを、少し熱い目にしてみました。自
分の手に当ててみて少し熱いかな?とおもったので聞いてみ
たところ、「熱くはない。」という、お返事が返って来まし
た。そのままの熱さで乾かせたので、早くに、乾きました。
ところが、次の方にも同じ熱さで試みてみて、尋ねてみた
ところ、「少し熱い。」というお答えが返って来ました。さらには、その次の方から
も、同じお答えが… もちろん、そのときには、乾かせるのに時間が幾らかかろうと
もぬるくして差し上げたことは当たり前のところです。
その折にですが、私には、ハッと気づいたことがありました。それは、あたかも、
稲妻のように閃きましたね。それは、少し痴呆がかかって、一昨年に逝くなった母の
ことでした。母は、当該施設にも、ディ・ケアーなどで一時期大変にお世話になった
ことがあります。その母も、世間の多くのみなさん方とも同じように、特養さんの順
番をひたすら長く待ちながら、結局は、その順番が回っては来ずに、A病院にてその
生涯を閉じました。早朝に、誰に看取られることもなく…
その入院の前に、母は、Bグループ・ホームにもお世話になり、そこで、右足のつ
け根の辺りの骨折をしてしまいました。それは、余りにも、脆すぎる骨折ではありま
した。そして、急遽入院、即手術という経過を辿ることを余儀なくされました。手術
としては中位のレベルのものでしたが、それは、無事に終わりました。ところが、そ
の結果は、それっきりの寝たきりの身となってしまいました。そのことは、諸々の状
況からして、ある程度は、致し方のないところだったのではないか とおもっており
ます。十分とは言いませんが、それなりには、納得はしております。そして、その入
院からの約5ヶ月目には、帰らぬひととなってしまいましたね。
そのときのことで、2つのことが、頭に残りました。その1つは、手術のあと、一
度だって「痛い!」と言ったことがありません。執刀されたお医者さまでさえ首を傾
げられる程でした。もう1つは、褥瘡(じょくそう。床ずれのこと…)のことです。
私が初めてそれを見たときには、正視に耐えられない、目を覆いたくなるような、恐
ろしい、恐ろしい褥瘡が、既に、出来てしまっていました。壊死した部分も、幾度か
に渡って、既に切除もされていました。ところが、それでも、母は私たちに向かって
一度だって痛いとも、辛いとも、何とも言うことはありませんでした。結局の
ところ、もう、感覚が無くなっていたかのようにおもえました。
冒頭のお方も、或いは、ドライヤーの熱さを熱いと感じられなかった背景には、既
に、母ともよく似たような感覚になられておられはしなかっただろうか?
一口に“介護”とは言っても、このホンの一例が示すように、ホントに理解をして
差し上げ、また心のこもった、温かいサービスをご提供して差し上げることの難しさ
を、僅かな、実習などのうちからも教えて頂きましたね。
追記) 次の文章は、高額医療費などの現在社会が抱える歪みのようなお話から端を発して、ある
お方が自己のHP上において認められたものの、極く極く、一部にしか過ぎません。
《 ……というようなことをぼーっと考えていくと、近い将来「姥捨て山」
的なものが必要とされる社会がやって来るかも知れない、と思いました。
そして、それに理論的に、かつ万人が納得するように反論する術を私は持っ
ていません。21世紀、そして未来の日本において「老いること」は何よりも
重い罪悪になるのかも知れません。 (注、アンダー・ラインは私による…) 》
大変に酷たらしい、そして悲しい、また寂しい… ことではありますが、
過去の日本には、「姥捨て山」(信濃がとりわけ著名ですが、実際には、
全国至るところにあったらしい。かっての深沢七郎さんの名作・楢山節考
には詳しい…)という、ある意味では、 極めて合理的な
極めて合理的な
システムや制度があって、そしてそれらが再び必要とさ
れる社会へと、果たして、なっていくのでしょうか?
介護の難しさ、その恐ろしさ、そして地獄の労苦、狂
気、家庭崩壊への大危機をさえ孕みながら……は、それ
を、実際に体験された極く少数の方々以外には、先ず、
殆ど分からないかとおもいます。このことは、はっきり
と、断言出来ます。
人間(ひと)は、今や、長生きし過ぎる不幸を、或い
は、荷なって生きているのかもしれませんね。そして、
それらは、明日にもあなたを襲って来るのかもしれないのですよ。
合掌!! (H16.9)
- このページの先頭に戻る -
| 黒 薙 温 泉 へ | 川 湯 温 泉 へ | いい湯だなぁ~ へ | 吉野温泉元湯 へ |
| 小 浜 温 泉 へ | 浜 村 温 泉 へ | 厳選リンクⅣ へ | カニの温泉宿 へ |
| 温泉一口メモ へ | 吉 良 温 泉 へ | いろいろな温泉 へ | 目次のみのページ |
| 雑書帖Ⅰ へ | 雑書帖Ⅱ へ | 雑書帖Ⅲ へ | 雑書帖Ⅳ へ | 雑書帖Ⅴ へ | 雑書帖Ⅵ へ | 雑書帖Ⅶ へ |