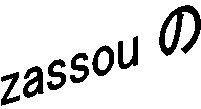
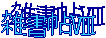
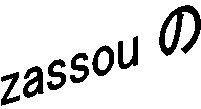
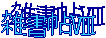
![]() お湯が 湧く わく ワク…
お湯が 湧く わく ワク…
1、 < 温泉 >の上に浮かぶ 大阪平野
温泉の掘削費は、深さ1メートルにつき、約10万円かかるそうです。従って、1千メートルでは、1億円と
いうことになりますね。
なお、温泉の掘削では高い実績を誇る奥ボーリング工業(兵庫県尼崎市)の技師(西川和史さん)は「
天然温泉としての人気が高まるから、(少々投資をしても、)10年くらいで元が取れる。」と、極めて、強気
な発言をされておられます。
地下から汲み上げる温泉が、一気に、増えたのはバブル経済のころですね。石油を掘るボーリング技術
を導入したために、掘削費も、かなり下がりました。
昔からある温泉(例、九州の阿蘇山周辺の温泉群など…)は、地下深くのマグマに熱せられたお湯が、
地表に湧き出たところが多いようです。
しかし、実際には、地面を掘るとその近くに何も火山がなくても、100メートル下がるごとに温度は平均に
して3度づつ上昇するそうです。従って、1千メートルを掘れば30度上がるので、地表の気温が15度ならば
45度のお湯が湧くという計算になります。

だから、少しでも深く掘らないと、温度は十分には上がりません。京都
盆地や奈良盆地では、数百メートルも掘ると、花崗岩などの硬質の基盤
岩に当ってしまうということのようです。ただ、今では、その基盤岩から
温泉を掘り出す技術も進んできています。進歩のさまを、まざまざと、知ら
されます。
さて、その問題の大阪平野なのですが、大阪平野の場合、基盤岩は
その深さが1千メートルから1,500メートルと、大変に深いそうです。
だから、かなり、掘削がし易いということになりますね。
その基盤岩の上に〔 水を通す砂や小石の層 〕と〔 粘土の層 〕とが交互
に積み重なっています。もちろん、その砂のなかは、水分も豊富です。
従って、その温められた水の上に、大阪平野は拡がっているということになりますね。
2、 深~い< 有馬(温泉)系 > 浅~い< 龍神(温泉)系 >
兵庫県には有馬温泉という、古くからの、温泉があります。有馬温泉は、ポカポカと、温まる“食塩泉”
です。
一方の、和歌山県の、龍神温泉はお肌がすべすべとなる(注、美人になるお湯としても著名…)アルカリ
性の“重曹泉”です。
近畿地方に点在する温泉の殆どは、このどちらかに、分類されています。それぞれに塩分や、マグネシ
ウムなどのさまざまな、有効な成分が溶け込んでいます。
先述の大阪平野を掘ってみると、基盤岩のすぐ上の地層から汲み上げた温泉は、その殆どが“食塩泉”
だそうです。鉄分も多く、《金泉》として知られる有馬温泉よりは鉄分は少ないけれど、塩分はむしろ有馬
温泉よりも多いところもあるらしい。
このことを、もう少し、難しく言えば、[ 化石海水 ]が食塩泉の成分となっているという説もあるそうです。
即ち、地層が積み重なるときに閉じ込められた海水が、50万年以上もの時を越えて、いま基盤岩から
しみ出しているという 訳です。
訳です。
日本地下水理化学研究所(大阪市)の鶴巻道二理事さんは「有馬温泉も、
大阪平野に湧く諸温泉も、同じ化石海水だろう。」とおっしゃっておられます。
もっとも、もっと浅い地層から汲み上げられたお湯の成分は、紀州の龍神温泉
によく似ているということのようです。
多分、その周辺の土の成分なりが、溶け出したからかもしれませんね。
ただ、平野部においてはその成分も薄いがために、現行の温泉法上では“
単純温泉”としてしか認めてもらえないことが多いようです。
お湯1キロのなかの成分が1グラム以上なければ、“重曹泉”とは、認めてもら
えません。
少しだけ、補足を、させて頂きます。
今でも、東大阪(市)の辺りを掘ると、割合簡単に井水(井戸水のこと)を得ることが出来ます。これは、
極めて浅いところにも水が豊富にあって、水脈が走っていることを物語っているのでないかとおもいます。
そういえば、大昔には、ここ・大阪平野は完全な海でしたね。
3、 またまた < ほんものの温泉 > とは ?
温泉は、一般的には、水の浮力でリラックスして、温熱効果では血行がよくなり、関節や、筋肉が柔ら
かくなるという効用に加えて、その溶けている成分が天然温泉の場合には、天然温泉ならではの効果を
生んでくれます。
温泉の医学にお詳しい鹿児島大学の霧島リハビリテーション・センターの田中信行教授は「温泉の成分
は、肌の表面のたんぱく質や油脂と結合し、千分の1ミリほどの薄い膜を作ります。この膜が大きな力を
発揮するのです。」というように説明されておられます。
即ち、水分と熱とを保つので、肌はしっとり、身体はポカポカと… その温熱効果は、お風呂上がりの後
も、長~く続きます。
なお、この効果を十分に引き出すには、お湯1キロ当たりの成分が、最低でも、1グラム以上は欲しい
とも云われています。
仮に、ご家庭用の浴槽(約200リットル)に、入浴剤を入れて温泉効果を楽しまれるとすると、最低でも
200グラムの成分を、即ち約10袋(但し、20グラム/袋…)の入浴剤を入れなければならないという計算
になりますね。
例えばですが、日本でも有数の濃~いお湯でもある、先の有馬温泉のお湯なら、その成分はお湯1キロ
当たり約40グラムとさえ云われています。入浴剤に換算すれば、約8,300グラム(即ち、約415袋…)に
相当することになります。
従って、『天然温泉は、この地球からの、ありがた~い、ありがた~い恵み…』とも、いえなくはありません。
ここで、もう少し、突っ込んで考えてみて下さい。
有馬温泉のお湯は、確か、1キロ当たり約40グラムとありましたね。それを、入浴剤に、換算すると、な、
な、な… 何と約415袋ともありましたね。ポイントのひとつは、実は、そこにもあるんですよ!
それでは、バブル期を中心にしてボーリングされ、誕生しているプチ(?)湯、即ちゴロゴロ温泉(実は、
この名付け親は、私なんです。安っぽく、ゴロゴロとあるから…)の類いの濃度は、果たして、一体どの
くらいあるのでしょうか?
この濃度も、お風呂の循環方式などと共に、大きな、大きな問題点 のひとつなのです。
のひとつなのです。
確かに現行の温泉法を満たす成分はある、一応は熱い… しかし、その濃度
となると、極めて、お粗末… 私たちは、最近、特にこんな温泉に入らされて
いはしないでしょうか?
みなさんは、普通、良くても成分があるのか、どうかのチェックまでしかされて
おられないのでは? もっとも、この点においては、私とて同様ですよ。
まさにこの点において、しじゅうからの toyochu さんが、いみじくも《 熱い井戸
水 》とまで酷評され、この私だって、それに何のためらいもなく同調した背景の
ひとつがあります。
仮に言葉を換えて言うなら、《 温泉もどきに近い温泉 》が、極めて多く存在
していることとなります。
なお、このことは、何も新規の温泉に限らず、昨今では、かっての大温泉の中にさえ、そうした温泉が
見え隠れし出しましたね。その生命ともいうべきお湯の枯渇などの、新たな、問題点を抱えて…
結論としては、やはり、ホントの温泉に行きあたることが少なくなってきました。
その温泉が、本来の温泉としての、その役割を果たす為にはこの濃度とも、実は、大きな、大きな関わ
りがあります。
これはホンの一例ですが、熱~い、熱~いお湯で知られている群馬県の草津温泉では、お湯を入浴
可能な適温にする為の水は使われていません。この気持こそが、ほんものを維持する為に、大切な心
構えのひとつともなるのです。
注) 1、今回は、朝日新聞社さんに、ずい分とお世話になり、これを完成させて頂き
ました。厚く御礼を申し上げます。
2、なお、水の比重は1ですから、1グラムとは(1ccのことであり、また)
1ミリリットルのことでもあります。従って、1キログラムとは(1、000
ccのことであり、また)1リットルのことでもあります。
| 黒 薙 温 泉 へ | 川 湯 温 泉 へ | いい湯だなぁ~ へ | 吉野温泉元湯 へ |
| 小 浜 温 泉 へ | 浜 村 温 泉 へ | 温泉があぶない!へ | カニの温泉宿 へ |
| 温泉一口メモ へ | 吉 良 温 泉 へ | いろいろな温泉 へ | 目次のみのページ |
自然保護をめぐる議論は、地方のひとよりも、むしろ自然を失ってしまった都会人の間で活発
ではなかろうか?
しかし、自然愛好家をもって任ずるひとのなかにも、身体の方が既に人為的にコントロールさ
れた快適さに馴染んでしまっているひとが多いようにもおもえる。
これはホンの一例だが、民宿に対してシティ・ホテル並みの設備を求めたり、高山の山小屋に
シャワーや水洗トイレを期待しながら、その一方では自然環境の保全を要望するといったジレンマ
を絶えずもちあわせている。なお、このことに関しては、私とて決して例外ではない。

われわれ大人がそうなのだから、ましてや生まれてこの方、コンクリート・ジャングル
のなかでしか行動をしたことのない子供たちに至ってはなおさらのことである。
小学校の林間学校に参画して、カブトムシなどを見た途端に、殺虫スプレーをかま
えた子がいたという話を聞いたことがあるが、あながち、作り話とばかりは言えない。
似たような話はいくつもある。
実際、開発や環境問題について語り合うことは、実に、難しい。 (H16.春)
| ニ リ ン ソ ウ |
谷間を下っていくと、一足先のところで、急に鳥が羽ばたいて林のなかへと逃げた。
実は、そこは、鳥たちの水場だったのだ。
こんなところに小さな流れがあるとはおもえない地形からして、水場の水は、この山の湧き水で
あることも分かった。
苔むした岩のいくつかには井戸端会議のあとの糞が沢山にあって、私がもしも立ち入らなかった
なら、どのような世間話を続けていたことかとおもう。
白い絹のような清冽な流れの始まりに、しばらくザックを投げ出して、時をも忘れて今しがた飛ん
でいった方向をじっと追ってみた。
とすると、ヒガラかコマドリか、特徴のある声で 「ツッピンツ」 「ピンピチカ
ララ」 と鳴いていた。
めったと外来者の入らない楽園で野鳥が憩うのは、至極、当たり前のこと
である。
少し悪いことをしたような気にもなった。
そして、そんな木々の間には、点々と『 ニリンソウ 』が早くも春を告げて
いた。
若き日の、怖い単独行での、楽しい瞬間でもあったなぁ~ (H16.春)
“なたね梅雨”とか、“花の前線”とか、“花冷え”とかいう言葉がよく使われますね。これらは
いかにも日本的な言葉のようで、私は、大好きです。
“桜の前線”が、この関西地方に、北上してくるのは例年3月の末から4月の初旬にかけて
です(地球温暖化の所為か、年々、早まって来ているようにはおもいますが…)
それが信濃路ともなると、約1ヶ月は、遅れるそうです。
その代わりに、里を訪れた遅い春は、桜や梅、桃に杏、そして花梨や
リンゴの白い花などもいっせい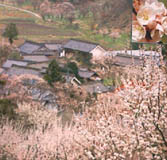 に咲き競わせるということのようです。
に咲き競わせるということのようです。
残雪を抱いたアルプスの雪解け水は身を切るように冷たいけれども、
極めて清冽なるものをおもわせられます。
そのような好季の信濃路を、私は、まだ歩いたことがありません。
是非とも、早い機会に、一度尋ねてみたいとおもっています。
(H16.春)
| 目次のみのページⅠ へ | 目次のみのページⅡ へ | 目次のみのページⅢ へ |

<サントリー・山崎蒸留所>
もう今更、私が、ご説明するまでもないくらいによく知れ渡っていますね。
かって、本能寺(京)で織田信長を討った明智光秀と毛利攻めから転戦した羽柴秀吉
との天下分け目の合戦のひとつ(俗には、山崎の合戦…)の、舞台ともなった天王山(
標高270.4m) その天王山系の伏流水を使っているここ・サントリーの山崎蒸留所
は、JR東海道線・山崎駅、または阪急京都線・大山崎駅近くで、その天王山の山すそに
立っています。
ここ・山崎蒸留所で使われている水は、名水百選にも選ばれた、“離宮の水”としても
知られている水無瀬神宮のものと同系統の水でもあります。
そして、その醸造を担当されておられる技師長さんは 「ウイスキーの味の50%は水
で決まり、蒸留までの工程で8、9割までが固まる。」 とも言われておられます。
今回は、その重要な要素のひとつでもある製造工程を、サントリーさんのご好意によって
見学させて頂きました。
良質の水をもつここ・山崎は、我が国においては、ニッカウヰスキーの余市(北海道)
蒸留所に続き、2番目にできた蒸留所でもあります。
その水、そして研ぎ澄まされた五感、さらには革新的な小宇宙(即ち、環境や進んだ製造
設備)… そうした諸条件のもとで、その結果として生まれた神秘にして、凝縮された
味や、香り… も、ここで、無料にて試飲させても頂きました。
なお、本HPの『ひまわりの会 Ⅱ』のところでも、この工場の様子などを、極めて若干
ですが、ご覧になって頂けます。
<アサヒビール・大山崎山荘美術館>
ここ・大山崎山荘美術館も、その天王山の、中腹に位置しています。天王山ハイキング・
コースの一角でもあります。
この山荘を築かれた関西の実業家・加賀正太郎さんは、若き日に欧州に遊学をされ、西洋
文化にも親しまれ、その見聞を大きく広められました。
そして、ここからの眺めを、ウィンザー城から見たテムズの流れにたとえたとも云われて
います。その眺めを眺めながら飲むコーヒーの味は、また、格別?…
垢抜けた日本庭園の外側には眼下に見下ろせる三つの川(木津川、宇治川、桂川)が、
ほぼこの地点で合流して淀川となって、枚方・寝屋川などを経て大阪湾に至ります。
なお、その対岸には、石清水八幡宮さまのある男山を望むこともできます。
このような山と川とに挟まれた狭い土地は軍事や交通の要衝でもあり、そしてまたそこを
見下ろせる山は、おのずとその価値が増したことは、容易に、理解できます。
さて、美術館の新館の方では、印象派の巨匠・モネの晩年の傑作“睡蓮(すいれん)”の
連作やマルク・シャガールなど… またジャコメッティやホアン・ミロ、イサム・ノグチなど
の現代彫刻の秀作も、展示されています(但し、展示作品は、都度変わりはしますが…)
その“地中の宝石箱”とも呼ばれる半地下の新館は、あの建築家、安藤忠雄氏の設計による
ものです。
また、本館の方では、アサヒビールの初代社長であった山本為三郎さんが収集された
“ 山本コレクション(河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチ…といった工芸作家
たちの作品に加えて、柳宗悦との親しい交流を通じて収集されたと云われている中国や、李朝
の古陶磁に、西洋の陶磁など…)”を鑑ることができます。
なお、ここは四季を通じて訪れる人も多く、自然と山荘・庭園とがまさに一体となった美と
やすらぎの空間として、芸術鑑賞のひとときを心ゆくまで楽しむこともできます。
但し、美術館の入館料として、600円が要ります。
《 千利休の茶室・待庵と… 》
実は、この地には、もうひとつの大きな、大きな見ものがあります。
それは国宝で、JR・山崎駅前にある、“待庵(たいあん)”のことです。
しかしながら、ここは、1ヶ月前までに“妙喜庵(みょうきあん、TEL. 075-956-0103… )”に
往復ハガキにて申し込まなければなりません。
但し、そのレプリカ(即ち、複製のこと…)については、阪急の大山崎駅近くにある
大山崎町歴史資料館にあります。こちらの方もお勧め致します(入館料:200円)
あの、著名な(千)利休の建てた茶室として、唯一現残するのがこの“待庵”なのです。
その点においてだけでも、大いに、関心をそそられますね。
利休が、時の人・秀吉に、切腹を命ぜられ、その折に茶室も解体させられました。
しかし、千家の再興が許された1594年以降に、天王山のお城から現在の“妙喜庵”に
移築されたとも云われています。
ただ、はっきりとしていることは、その待庵が当時の茶室の常識を越えた、斬新なもので
あったということのようです。広さはわずか2畳、壁の隅に丸みを持たせ、天井も斜めに
張った……
狭くても広がりをさえ感じさせる茶室… それはウイスキー造りには欠かせない樽にも共通
する、これこそが、真の革新的な小宇宙?
その閉ざされた空間の中で、蒸留仕立ての透明な液体は、時を経て琥珀色に変わっていく…
自然の恵みを、自然の力が、琥珀色に変えていく…
後述の信治郎の時代をさかのぼること300余年… 千利休も、また、この地での実験を
あれこれと試みていたのでしょう。この名水の里において…
だが、それ以上に、“待庵”の存在については私に大きな、大きな関心を抱かせてくれた
ものがあります。 それは ↓↓
先述のサントリー・ウイスキーの蒸留所が、あまた名水のあるなかで、何故この地・山崎
でなければならなかったのでしょうか?
そこにはサントリーの創業者・鳥井信治郎と千利休、この偉大な二人の先人が、期せず
して、この地を選んだ大きな、大きな理由、さらには謎めいたようなものさえありそうな気がしない
訳でもないのですが…??
例えば、例えばですよ、温度差のある三川の合流で霧が生じ、その霧がもたらす湿潤がウイ
スキーの熟成に適する(?)……
これとも似た微妙な、微妙な条件の積み重ねが、この偉大な二人をして、その選択を決定的
にさせた…とか???
言うなれば、時空ともに狭隘な山崎の土地そのものが、まか不思議なエネルギーをも秘めた、
これこそが、真の革新的な小宇宙なのかな??
どうも、オレは、或いは常に夢見る人でしかないのかな~~ ??…
☆☆ このページの TOP へ ☆☆
☆☆ 次ページ へ ☆☆